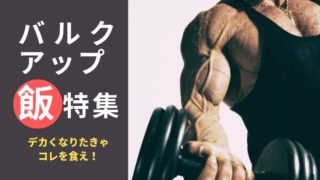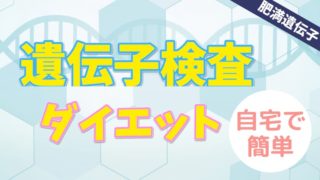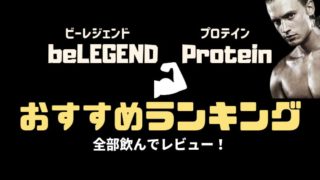最新の情報を探しています。
Rito(Rito)です!
最近書店に行ったときに発見した「トロント最高の医師が教える 世界最新の太らないカラダ」という本を読んでいます。

価格は1600円+税でした。
結構分厚くて、1日では読み切れなそうなので分割して読んでいこうかなぁと。
全部で6部あります。
- 「トロント最高の医師が教える世界最新の太らないカラダ」がどんな内容なのかザックリ知りたい。
- ダイエットの情報を探している。
第1部:肥満の事実

第1章:ダイエットの黒歴史
第1章では「ダイエットの黒歴史」ということで、今までのダイエットの否定から入っていきます。
「痩せなさいという医者が太っている」
「糖質制限は最新の理論とは違う」
今までのものとは違うぞ!という導入部分ですな!
やっぱりね、この本はひと味もふた味も違うんだというところを導入部分で見せつけて、読者を惹きつける。
常套(じょうとう)手段ですね。
おそらくアメリカ人に向けて書いているのか、アメリカでのダイエットの歴史の話が多い印象。
【例えば】
脂質を悪とした時期がある。
↓
炭水化物を摂るようになる。
↓
太る。
そんな感じ。
脂質にばかり目がいっていたせいで、糖質にはあまり目を向けてこなかったようですね。
第2章:残酷な事実
この章では、遺伝と肥満について書かれていました。
という残酷な事実を突きつけられます。
そ、そんな・・・。
うちのバァちゃん、糖尿病だったんですけど…。
双子の実験や養子の実験など、科学的な結果からそのことがわかります。
[nlink url=”https://rito105.com/obesity-heredity/”]
しかし、30%は自分がコントロールできる部分であり、遺伝の70%部分もそのことを理解していれば違った結果になる。
肥満の根本原因は、インスリンが関係している。
そして第1部の最後には、インスリンが肥満と関係していると断言。
ほぉ、インスリン。
うちのバアちゃん、インスリン注射打ってました…。
自分で…。
第2部:「カロリー制限」という幻想

第3章:「食事量は関係ない」と断言できる。「削ってもムダ」だと示す膨大なデータ
肥満になる原因は
摂取カロリー>消費カロリーだと考えていますよね?
私もそう考えていました。
しかしこの本の中では、それは間違いだとされています。
また、間違った仮説とその理由を様々な論点から書かれます。
例えば、「何からカロリーを取ろうが同じカロリー説はおかしい。」とか。
オリーブオイルから摂取したカロリーと砂糖から摂取したカロリーが同じワケあるか!ってね。
確かに。
摂取カロリーが減ったのに、肥満が増える不思議。
そして最新のデータでは「アメリカ」だけでなく「イギリス」でも、摂取カロリーが減っているのに肥満率が増えるという結果が出ている。
そしてカロリー制限には様々な危険性があると指摘されます。
- 体温が下がる
- 心拍数が減る
- 血圧が下がる。
- 集中力がなくなる。
- 髪の毛が抜ける。
など、様々なデメリットが出てきます。
特に最後の項目「髪の毛が抜ける」はヤバイ。
やばすぎるだろ…。
太る原因はホルモンのバランスじゃい!
第4章:運動神話 残念ながら、走っても走っても、やせません

この章でも様々なデータを元に、運動では「ほとんど」やせないことが証明されます。
p.100の「運動しない国」ほどやせの人が多い
では、日本がグラフの一番下に表示されていてなんだか複雑な気持ちに(笑)
運動しないけど、ヤセが多いんですかね!
運動をするとより食べたくなってしまって、食べ過ぎちゃったりもしますよね。
しかしながら、「走っても走ってもやせない」というのはちょっと狙いすぎ。
実際に実験で痩せている。
そのやせ方が「予想よりもやせない」ということ。
例えば予測で15kg痩せるところが5kgしか痩せなかった。
そういうこと。
第5章:過食のパラドックス「食べ過ぎると太る」も大嘘?
運動はダイエットの5%くらいといったあとは、食べ過ぎもまたちょっと違うという話。
1日に5000kcal以上食べて、自らの身体で実験した例が載っていました。
食事の内容によって、太り方が全然違いましたね。
同じ5000kcalオーバーの食事だけれど、中身によってこれほど大きな差が出るとは…。
体重の設定値
体には「設定値」が決められていて、その設定値に合うように体が調整して体重が増えたり減ったりする。
例えば体重の設定値が70kgの男性がいるとしよう。
彼が食べすぎて75kgになった場合、体は元の70kgに戻ろうとして
・満腹ホルモンを出して食べないようにする。
・カロリーを制限しようとする。
などの働きを勝手にやってくれる。
逆に65kgに減ったとすると
・満腹ホルモンを出さないようにする。
・カロリーを摂るようにする。
という形で、設定値(この場合は70kg)に戻ろうという働きをするようになるのだそう。
ああ、素晴らしい。カラダくん。
キミに全て任せていいんだね?
でもその設定値って、高くなってたらヤバイんじゃ…。
そう、その体重の「設定値」が高ければ太った状態に近づいていくし、低ければ痩せの状態に近づいていくのだ。
仮に設定値が68kgなら…?
設定値を低くすれば、体は勝手に痩せていく。
ではその設定値が低く設定されれば、体が勝手にその設定値に向かってくれるというわけだけれども。
じゃあその設定値は何によって決まるのか?
その話は、第3部で!!
えええええ!!!
・体には「設定値」があり、太っても痩せても、体がその設定値に調節しようとする。
1部2部の総括

第1部と第2部を読んでの感想は
とにかく「炭水化物が良くないぞ」ということ。
アメリカでは一時期「脂肪」こそ良くないということで、低脂質ダイエットが提唱されたがその結果、逆に炭水化物の摂取量が増えて、肥満が増えてしまったと。
ではなぜ炭水化物が良くないかというと、インスリンの分泌に関わるから。
インスリン・インスリン・インスリン。
ダイエットにはこの「インスリン」がものすごく深く関わっているということが、1部2部から読み取れましたね。
インスリンといえば、ばあちゃんがインスリン注射打ってたイメージしかない私ですが…。
自分も可能性があるんだよなぁ…。
糖尿病。
さて、気になったのは最後の「設定値」
勝手に体が調節してくれるということですが、この設定値は何によって決まるのか。
低く設定するにはどうすればいいのか。
第3部が楽しみになってきました!
それでは!