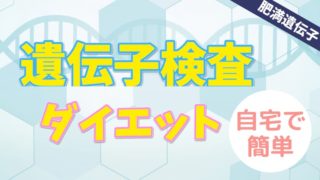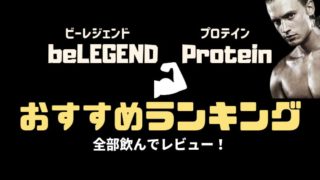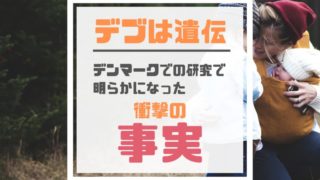「ダイエットのためにランニングを始めたけれど、なかなか効果が出ない。」
「むしろ逆に太ったかもしれない…。」
正しい知識がないと、有酸素運動はダイエットに逆効果に働くかもしれません。
カラダづくりのプロ山本義徳先生が解説してくれていましたので、その話を参考にまとめていきます。
この記事では、「有酸素運動はダイエットに逆効果」になってしまう理由と、「正しい有酸素運動」について書きました。
有酸素運動で痩せない理由・間違った有酸素運動の仕方を知ることで、痩せる有酸素運動の仕方に変えていくことができます。
- なぜ有酸素運動は逆効果になってしまうのか。
- どのようにすれば効果的な有酸素運動になるのか。
- 効率の良い運動の仕方
ダイエットに有酸素運動が逆効果である理由
理由1.心肺機能を鍛えるということは、カロリーを消費しないようにすること。
ダイエットのために一生懸命に走っている人は、カロリーを消費するために走っていると思います。
マラソンランナーの人たちなどは心肺機能を鍛えるために走っています。
同じ「走る」という行為をしていますが、目的は違いますね。
カラダは省エネを目指す。
走るとカロリーが消費されるというあたり前のことなのですが、カラダは「消費カロリーをいかに抑えるか」という点で進化・成長・適応していきます。
エネルギーをたくさん使ってしまうと、生きるためのエネルギーがなくなってしまいますから、カラダとしてはエネルギーをなるべく使わないようにしたいわけです。
毎日走っているマラソンランナーの人たちが、長距離を走れるのは「エネルギー効率がいい」つまり「少ないエネルギーで動けるカラダ」になっているからなのです。
カラダはエネルギーをなるべく使わないようになる。
理由2.UCP(Uncoupling Protein)が関係している。
有酸素運動をしていくと、『UCP』というものが減っていきます。
■ UPCとは
UCPとはUncoupling Protein、「脱共益たんぱく質」のことです。
脱共役タンパク質(英:Uncoupling protein)は、酸化的リン酸化のエネルギーを生成する前に、膜間のプロトン勾配を浪費することができるミトコンドリアの内膜のタンパク質である。脱共役タンパク質は、Uncoupling proteinの頭文字を取ってUCPと略されることが多い。
哺乳動物では5つのタイプが知られている。
・UCP1:サーモゲニン(en:Thermogenin)として知られている
・UCP2
・UCP3
・SLC25A27:”UCP4″ として知られている
・SLC25A14:”UCP5″ として知られているATPを生産する替わりに、エネルギーが熱を生成するために使用されるため、脱共役タンパク質は冬眠時の運動を伴わない熱産生のような正常な生理機能を果たしている。
UCP1は褐色脂肪細胞にのみ存在し、UCP2は白色脂肪細胞、免疫系細胞、神経細胞などに認められ、UCP3は主に骨格筋、心臓などの筋組織において多く存在する。糖尿病患者の骨格筋においてUCP3タンパクの合成が著明に低下していることから、熱産生あるいは脂肪代謝に関連していると考えられている。
ノルアドレナリンが褐色脂肪細胞上のβ3受容体に結合すると、UCP1が生成され、ミトコンドリアで脱共役が起こり熱が産生される。日本人を含めた黄色人種ではβ3受容体の遺伝子に遺伝変異が起こっていることが多く、熱を産生することが少ない反面、カロリーを節約し消費しにくいことから、この変異した遺伝子を節約遺伝子と呼ぶことがある。
簡単にまとめると。
- UCPは体温を担うたんぱく質
- 私たちのカラダはATPをエネルギー源として使っている。
- ATPを作るときに無駄な熱が出る。
- 無駄な熱を作り出すのがUCP
- 赤ちゃんの体温が高いのは、UCPが多いため。
- 歳を取ると体温が低くなるのはUCPが減るため。
- マラソンランナーはUCPが少なくなる。
体温が下がるということは、基礎代謝が下がるということですね。
基礎代謝でもっとも割合が大きいのが「体温の維持」です。
基礎代謝やカロリーなどの詳細については以前まとめた記事が参考になるかと思います。
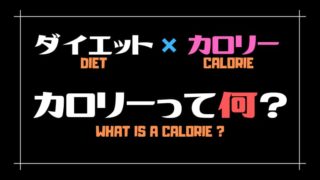
有酸素運動を続けていくと、カラダが効率化される。
カラダ的には少ないカロリーでエネルギー源であるATPをたくさん作れたほうがいいですからね。
有酸素運動を続けていくと、エネルギー(ATP)を作ったときに出る無駄「UCP」をなるべく出ないようにカラダが適応していきます。
すると、普段何もしていないときの消費カロリーが低下してしまう。ということなんですね。
有酸素運動のやりすぎは代謝を落としてしまう。
理由3. 有酸素運動をやりすぎると速筋線維が遅筋線維に変わりやすくなる。
有酸素運動をやりすぎると「速筋線維」が「遅筋線維」に変わりやすくなります。
速筋線維
速い速度で収縮し、大きな力を瞬間的に発揮する。瞬発力に優れた筋肉。
遅筋線維
遅い速度で収縮し、小さな力を長時間発揮し続けることができる。持久力に優れた筋肉。
速筋線維のほうが大きくなりやすい。
有酸素運動をやりすぎると、トレーニング効果が落ちる。
理由4. やりすぎると疲れが溜まってしまう。
有酸素運動はついついやりすぎてしまう傾向があります。
「1時間~2時間走ってきた!」という人がいるように。
- 単純に疲労物質が体内に蓄積する。
- 男性ホルモンが低下する。
- コルチゾールが増える。
効果的な有酸素運動のしかた:時間やタイミングなど。
有酸素運動は「やりすぎると」ダイエット的にはデメリットが発生してしまうことがわかりました。
では、効率よく有酸素運動を行うにはどのようなタイミングで行えばよいのでしょうか?
有酸素運動は1回30分。週に2回~3回
有酸素運動を効率良く行うには、2つのポイントを守ったほうが良さそうです。
- 1回30分以内にする。
- 週に2回~3回程度にする。
通勤や通学などで、駅まで10分歩いている人はそれだけで往復20分の有酸素運動をしていることになります。
そこに加えてさらに有酸素運動をしてしまうと、やりすぎになってしまう可能性もあります。
有酸素→ウエイトトレーニングに切り替えていこう。
有酸素運動ではなく、ウエイトトレーニングを行ったほうが体脂肪を落とせると山本義徳先生はいいます。
有酸素から筋トレに切り替える。
もしくは、筋トレと有酸素を組み合わせることでダイエット効果を更に高めることができますね。
山本義徳先生が教える、ダイエットに効く正しい有酸素運動のやり方まとめ
有酸素運動はやりすぎると逆効果になる可能性があるということがわかりました。
最後にまとめて終わりにしましょう。
- 有酸素はやりすぎるとUCPが減る。
- UCPは体温を担うたんぱく質。
- 体温が下がると基礎代謝が下がる。
- やりすぎると疲れがたまる(コルチゾールなど)
- 速筋線維が遅筋線維になってしまう。
- 1回30分以内・週2回か3回が効率的。
- ウエイトトレーニングに切り替えたほうが体脂肪は減る。
筋トレと有酸素。
バランスよく行って、効率よく体脂肪を落としていきたいですね!
効率よく体重を落としていく場合は、サプリメントを有効に使っていく必要があります。
山本義徳先生がオススメする「減量中」に飲むべきサプリメントもあわせてどうぞ。